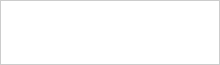「若手の離職を何とかしたい…」。そんなときに手にとりたいのが井上洋市朗先生のご著書「離職防止のプロが2000人に訊いてわかった! 若手が辞める「まさか」の理由」です。
退職者300人に聞いて分かった本当の離職理由
本書の魅力は、300人以上の退職者へのインタビューを通して見えてきた「辞める本音」。
でも驚くのは、退職理由の聞き取りですら、万能ではないという指摘です。
なぜなら、
本人も、自分がなぜ辞めたのか、うまく言語化できていないことが多い
から。
つまり、表面的な言葉の奥にある“モヤモヤ”にこそ、退職の真因がある。
その深層をていねいに掘り下げ、対策の方向性を導いているのが本書の強みです。
「福利厚生を充実させれば、辞めない」は幻想だった?
大企業がよくやるのが、引っ越し一時金や家賃補助などの「手当」強化。
でも、それって本当に効いてるんでしょうか?
本書では、「50万円の転勤手当」が離職防止にはほぼ効果なしとバッサリ。
なぜなら、こうした制度は「不満の解消」にはなっても、「やりがいの実感」にはつながらないから。
これは、あの有名なハーズバーグの動機づけ理論でも説明されています。
-
衛生要因(給与や制度)は、あって当たり前。なくなると不満。
-
動機づけ要因(やりがい・成長)は、あって初めて満足。
なるほどと思いつつ、さらに本書ではこんな指摘も——
動機づけ要因は定量化が難しく、うまく扱わないと空回りする
結局、「これさえやれば辞めない」は存在しないという、現実を突きつけてくれます。以前書評として取り上げた「離職防止の教科書」でも同じ結論ですけどね…。
若手離職防止のカギは、課長にあり
じゃあ、誰がこの難しい個別対応の最前線に立つのか?
答えは明確です。
現場の上司=課長こそがカギを握っている。
本書のラストでは、産業能率大学の調査データが紹介されています。
2018年から2023年にかけて、「課長に求められる力」が大きく変わっているのです。
-
「職場の構想を描く力」:12位→2位
-
「事業戦略を立案する力」:17位→5位
つまり、若手は“未来を描ける上司”についていきたいのです。
制度や待遇ではなく、「この人と働きたい」と思えるかどうか。
最後に:離職率を下げたいなら、個別対応力を磨け
離職を防ぐ決め手は、「気の利いた制度」でも「高額な手当」でもなく、一人ひとりに向き合う“課長力”です。
すべての若手が求めているのは、
「自分の可能性を信じてくれる人」との出会いかもしれません。
この本を読むことで、その「目の前の一人」にどう向き合うかが変わる——
そんな一冊です。
画像はアマゾンさんからお借りしました
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- 離職防止


 RSS
RSS