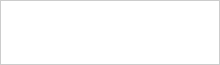「心理的安全性」—— この言葉、ここ数年ですっかり定着しましたよね。
- 「心理的安全性が高い組織は、生産性が上がる!」
- 「社員が自由に発言できる環境が大事!」
こんな話を聞くと、「なるほど、いいことばかり!」と思いがちですが、本当にそうでしょうか?
心理的安全性が高すぎると、企業の業績が落ちる?
テルアビブ大学のエルダーらの研究によると、心理的安全性が高すぎると企業の業績がむしろ低下する可能性があるとのこと。
【MBAの心理学】テルアビブ大学のエルダーらは、高すぎる心理的安全性はかえって企業の業績を落とすことを指摘。とくに、ルーチン業務の遂行が弱くなることが懸念される。これを避けるために提唱されたのが、「集団的説明責任」。リーダーは、時には心理的安全性を下げる手を打つ pic.twitter.com/vUgh3Swhrt
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) February 15, 2025
要は、「みんな仲良しで意見は言いやすいけど、仕事の締まりがない…」みたいな状態ですね。
心理的安全性=「意見を言わない」ことではない!
最近、若手社員の会議での振る舞いについてこんな話を聞きました。
「反対意見を出すと、相手の心理的安全性を損なってしまうから言えません…」
…ちょっと待って、それ違います!
心理的安全性とは、本来こんなものです。
✅ 間違いを認めても大丈夫
✅ 助けを求めても大丈夫
✅ 意見を言っても大丈夫
むしろ、「反対意見を言えない組織」は心理的安全性が欠けている証拠。
なのに、日本では「みんなが穏便に過ごせること=心理的安全性」みたいな誤解が広がっている気がします。
日本人の「表面的なマネジメント導入」、もうやめませんか?
実は、こういう欧米発のマネジメント手法を表層的に取り入れて、本質を見失うのは、日本のビジネス界では珍しくありません。
リストラクチャリング(本来は「事業再構築」)が、単なるリストラ(人員整理)になった
1 on 1(本来は「上司と部下の対話の場」)が、部下の話を聞く時間になった
そして今、「心理的安全性」も、ただの「ぬるま湯組織をつくる言い訳」になりつつあります。
「本質を見抜く」マネジメントを
心理的安全性は、チームの生産性を高めるために有効な概念です。
でも、それを「何でもOKの甘やかし環境」にしてしまったら、逆効果。
・意見が言いやすい環境を作ること
・同時に、結果に対する責任も明確にすること
このバランスを取るのが、本来の「心理的安全性」のある組織なのではないでしょうか?
そろそろ、日本のビジネス界も「欧米発のトレンドを盲信する時代」から卒業して、物事の本質を見抜く力をつけるべきと感じます。
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- 心理的安全性


 RSS
RSS