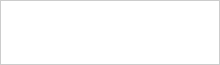目次
「セラミック・フィーバー」の光と影──大企業が去り、中小企業が成功した理由
「セラミックス・フィーバー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
1980年代、日本では新素材「セラミック」を産業分野に活用しようとする動きが盛り上がり、「フィーバー」とまで呼ばれるほどの熱狂を生みました。自動車エンジンの金属部品をセラミックに置き換え、冷却不要のエンジンを実現する──そんな未来が描かれていました。
しかし、結果としてこのフィーバーは「失敗」に終わります。いま私たちが乗っている車のエンジンは、結局すべて金属製のまま。参入した大企業も事業化を断念し、撤退を余儀なくされました。
なぜ、「国家主導のイノベーション」は失敗したのか? そして、その裏で成功した企業とは?
産業政策の裏にチャンスあり?──「すきま」を狙った中小企業の逆転劇
セラミック・フィーバーの背後には、経済産業省(当時は通商産業省)の政策がありました。高度成長期を経て、「追いつけ、追い越せ」から「日本発の技術革新」へとシフトするための国家戦略でした。
ところが、この壮大な構想は大企業の撤退によって瓦解。しかし、同じセラミック技術を使いながら、静かに成功を収めた企業がありました。
それは、「エンジン」ではなく「電子部品」の分野でセラミックを活用した中小企業です。大企業が派手なイノベーションを狙うなか、小さな市場で着実に技術を磨き、競争力を確立していったのです。
この「すきま」を狙った戦略こそ、現在のスタートアップにも通じるヒントではないでしょうか?
「すきま」はどこに生まれるのか?──ベンチャーが狙うべきポイント
ベンチャーが成り立つ背景には、
✔ 技術革新──新たな技術が市場に登場し、大企業が対応しきれないフェーズが生まれる
✔ 市場の変化──消費者のニーズや産業構造が変わり、新たなビジネスの余地ができる
といった要素があります。
そして、ここに「政府の産業政策」という第三の要素が加わることが、今回のセラミック・フィーバーの例から見えてきます。
政府が推進するプロジェクトや補助金政策の裏には、思わぬ「すきま市場」が生まれる可能性があるのです。
次に狙うべき「すきま」は?──政府の動きを見極めよう
新規事業を考えるうえで、政府の産業政策をチェックすることは意外と重要な視点です。
✅ 政府が大きなプロジェクトを推進しているとき、その周辺に「誰も手をつけていない市場」が生まれていないか?
✅ 大企業がこぞって参入している分野で、彼らが見落としているニッチな領域はどこか?
この視点を持つことで、新たなビジネスチャンスが見えてくるかもしれません。個人的には、J-Startupの周辺領域とか面白そうな気がしています。
ちなみに、このテーマに関心がある方は、日経新聞で連載されている一橋大学・島本実教授の「産業政策の意図せざる結果」も必読です。ベンチャー界隈の方は、ぜひチェックしてみてください。

この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- スタートアップ
 RSS
RSS