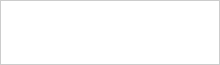子供の教育って難しいですよね。先日も尊敬するコンサルタントの方と、「中学受験はありかなしか」という議論をしましたが、結論は出ませんでした。「難しいですよねぇ…」で終わってしまって。
その難しさの根源は、測定することができないことにあります。別に有名中学校に進学することがゴールではないわけで、「どういう状態に達したら成功なのか」が定義しにくいものです。
結果として、子供の教育の成否には哲学的な考察が関わってきます。たとえばこれ。
【MBAの心理学】オーストリアの哲学者イヴァン・イリイチは、1970年に出版した「脱学校の社会」で学校教育を批判。「学びは本来、自分の好きなように行える自由な活動であるはずなのに、学校はそれを『教わる』という受け身の活動に変えてしまいます」、と #心理学 #MBA pic.twitter.com/wbucSBTvbI
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) April 9, 2025
まぁ、言いたいことは分からないではないですが、「だったらどうするの?」という次のアクションが見えませんね。
この難しさを加速させるのが「臨界期」という概念。
【MBAの心理学】アメリカの言語学者エリック・レネバーグ博士は1967年に出版した「言語の生物学的基礎」で学習の臨界期仮説を提唱。その後、ニューポート、ジョンソン博士の移民の子供の英語学習の調査により、この仮説はきょうかされた #心理学 #MBA pic.twitter.com/qZnJu075m2
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) April 9, 2025
もしも、何かを学ぶには適した年齢がある事-つまりは、その時期を逃すと学習が大きく損なわれる-が真実ならば、何をどの時期に学ばせるかは余計に難しいことになります。
ましてや、オリンピック競技においては、このような特性があるとすれば、難しさはなおさらですね。
【MBAの心理学】ゲント大学のローエル・バイエンスらはアテネオリンピック出場者を調査し、その競技を始めた年齢を調査。実は競技によって結果は異なり、水泳は幼少期に始めた選手が多い。一方、ボート競技は10代後半から初めてもオリンピアンになれる #心理学 #MBA pic.twitter.com/OB3R0hUJN3
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) March 31, 2025
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
 RSS
RSS