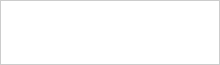ボーカロイド、と聞いてピンときますか?「初音ミク」に代表される、コンピューターが歌を歌う音楽技術です。
これが、今や世界的なブームになっているという事実に驚かされました。そんな衝撃を受けたのが、先日のNHKスペシャル「日本発”ボーカロイド文化”」。
でも、なぜこれほどまでに人気なのでしょうか?
ボーカロイドがもたらした「プロシューマー化」
この現象を自分なりに解釈すると、ボーカロイドは音楽の世界に「プロシューマー化」をもたらしたと言えます。
「プロシューマー(Prosumer)」とは、「プロフェッショナル(Professional)」+「コンシューマー(Consumer)」の造語。つまり、一般の消費者がプロのように創作し、発信する時代が来たということです。
YouTubeが映像分野でこの流れを加速させたのと同じように、音楽の世界ではボーカロイドがその役割を果たしました。
これまで楽曲制作には高いハードルがありましたが、ボーカロイドの登場によって「自分で作って、すぐに発表できる」時代が到来。その結果、個人のクリエイターが世界中に音楽を届けられる環境が整ったのです。
プロシューマーがプロフェッショナルへ──新時代のスター誕生
さらに興味深いのは、プロシューマーとして音楽を作り始めた人たちが、いまやプロとして活躍していることです。
NHKスペシャルでは、次のようなアーティストが紹介されていました。
✅ Ado
✅ YOASOBI
✅ きくお
彼らはボーカロイドを駆使し、ネットで楽曲を発表するところからキャリアをスタート。そして、いまや世界中にファンを持つトップアーティストになっています。
これこそ、プロシューマー文化がもたらした新たなスター誕生の流れです。
ボカロ文化は「心の拠り所」なのか?
一方で、NHKスペシャルの取り上げ方には少し違和感もありました。
番組では、「生きづらさを感じる若者がボーカロイド楽曲に救われた」という視点が強調されていました。でも、それって本当にボカロ人気の本質でしょうか?
確かに、歌詞に共感する人は多いでしょう。でも、海外も含めた熱狂ぶりを見ると、単純に「音楽としてカッコいいから聴いている」という層のほうが圧倒的に多いように思えます。
論より証拠。聴いてみたら納得した
こういうときは、頭で考えるよりも実際に体験するのが私の流儀。
さっそくSpotifyで前述のアーティストを聴いてみましたが… Adoさん、めちゃくちゃカッコいいですね。
特に「唱」とか、予備知識なしに聴いても「これはハマるわ」と思いました。
ボーカロイド文化は、単なる一過性のブームではなく、新しい音楽のあり方を示しているのかもしれません。
「プロが作った音楽を消費する」時代から、「誰もが音楽を作り、発信する」時代へ。ボーカロイドが生み出したこの流れは、これからさらに加速していくのでしょう。

この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- サブカル
 RSS
RSS