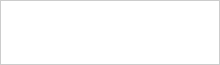先週の「MBAの心理学」は、教育哲学シリーズです。元ネタは孫泰蔵さんの冒険の書 AI時代のアンラーニングから。
特に今回テーマになっているのは子供の教育。
実はこの分野、昔から色々な工夫がされています。たとえば、これ。
【MBAの心理学】イギリスのジョセフ・ランカスターは1799年頃ロンドンで小学校を開設。先輩(モニター)が後輩を教えるというカスケード型の教育システム、能力別クラスを「発明」した。1862年にはサミュエル・ウィルダースピンの考案したギャラリー方式と合体し、効率的な教育を提供した pic.twitter.com/ObXUdddwsw
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) March 27, 2025
1799年と言えばフランスでは革命の後で、個人の権利が確立されているころでしょう。これがイギリスにも伝播して、幼年期からの教育に力を入れ始めたのでしょうか。
ちなみに日本では、松平定信による寛政の改革が終わったころ。当時の日本の識字率は世界的にも高かったという説があり、日本でも教育には力を入れていたようです。こういう蓄積があったからこそ、その後の明治維新や国力の発展に繋がったのでしょう。

この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
 RSS
RSS