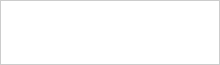「あの部下、ひょっとしたら止めてしまうのでは?」そんな危機感を持つ事ってありますよね。あるいは逆に、兆候が全くなかったのに突然退職を告げられて、「なんで気づかなかったんだろう」と悔やんだり。
そんなときに対策の指針になるのが藤田耕司先生のご著書、「いま部下が辞めたらヤバいかも…と一度でも思ったら読む 離職防止の教科書: 人手不足対策の決定版」です。
離職防止には「当たり前のことを当たり前に」
読後の感想を一言でまとめるなら──
「離職を防ぐには、当たり前のことを当たり前にやる」
これに尽きます。
でも、その「当たり前」が、意外とできていない。
たとえば、部下を叱るときにこんな配慮、していますか?
-
プライドを傷つけない
-
叱る“目的”を忘れない
-
叱りながらも、自分を俯瞰して見る(=メタ認知)
これ、言われてみればその通り。でも、怒っている最中に「メタ認知」できる人、どれだけいるでしょう?
個別対応こそが離職防止のカギ
本書のもう一つの学びは、「個別対応の重要性」です。
「最近の若者は…」なんて一括りにしてはいけない、と。
その指針となるのが、以下のフレームワークです。
| 意欲・能力の高さ | |||
| 上位 | 中位 | 下位 | |
|---|---|---|---|
|
新人若手 20代 |
ホープ | ルーキー | 問題児 |
|
中間世代 3-40代 |
エリート | 現場牽引者 | 未開花者 |
|
年長世代 50代以上 |
経営幹部 | 中間管理職 | 窓際社員 |
年代とスキルレベルのマトリクスで「辞める理由」が異なるため、それに合わせた対処が必要だと教えてくれます。
離職防止に効く「傾聴」のテクニック、知ってますか?
本書のノウハウにさらにプラスアルファするとしたら、具体的な行動です。たとえば、上司が部下の話を徹底的に聞くという「当たり前」の行動が、具体的にはどのようなものなのかの解説があると、読者が現場で活かすときにより参考になるでしょう。
-
部下と正対せず、90度で座る
-
語尾を繰り返して相づちする(例:「大変だったんですね」)
-
相手のうなずきとリズムを合わせる
こうした“聞く技術”を意識するだけで、部下の本音を引き出す確率は格段に上がります。
まとめ
結局、部下が辞めるのを防ぐために必要なのは、
特別なスキルやツールではなく、日々の当たり前の積み重ねなんですよね。
でもその“当たり前”が、忙しさや慣れで見えなくなってしまう。
本書は、それをグッと引き戻してくれる一冊でした。
「今は大丈夫」と思っている人ほど、早めのチェックをおすすめします。
画像はAmazonさんからお借りしました
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- 離職防止


 RSS
RSS