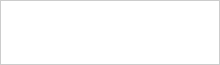「二宮金次郎」ってどんなイメージがありますか?銅像の、薪を背負って本を読んでいる人…というのが多くの人の一致するところでしょう。
でも実際は、それはごく一部。本当は奥の深い農業/農政の改革者だと気づかされました。それが、童門冬二先生のご著書、「小説 二宮金次郎」です。
二宮金次郎が説く、褒めると叱るの比率
私が二宮金次郎に興味を持ったキッカケは、「フィードバック」から。現代の欧米においては、「ゴットマン比率」と呼ばれる、褒めると叱るの適正割合が研究によって提唱されています。では、日本はどうなんだ?というときに出てきたのが、二宮金次郎の言葉。
可愛くば、五つ教えて三つ褒め、二つ叱って良き人となせ
ゴットマン比率よりも「叱る」の割合が高くなっていますが、それは日本では、ましてや昔の農村社会では人間関係が固定的だったためと考えれば納得です。
そして、この延長線上で「いもこじ」という言葉に行き当たりました。これは、グループ討議によってアイデアの洗練、人間の徳の向上ができるというもので、まるで水を張った桶に里芋を入れてぶつけ合うと汚れが落ちる様子から名付けられたものです。このような農村変革手法を確立しているということで、ガゼン興味を持ったのです。
組織変革者、二宮金次郎
実際に「小説 二宮金次郎」を読んでみると、
想像よりも深かった
というのが率直な感想。二宮金次郎の改革は、実は農村だけでなく、その農村の所有者たる武士階級までおよんだというのがビックリです。考えてみれば当時は6公4民などの超重税社会。武家の台所が苦しいままでは農村が裕になるはずもなく、言われてみれば当然と気づきました。
ちなみに、二宮金次郎は小田原生まれで、当時の小田原藩主は大久保家。有名な「彦左衛門」の家系(直系ではない)。そういえば、徳川草創の頃からの忠臣であった大久保家は、江戸幕府設立後は冷遇されていた、なんて話を聞いたことがあるような気がします。つまりは小田原藩も火の車であったがゆえに、農民階層宇出身の二宮金次郎が活躍する余地があったと言えましょう。
その後は栃木県の桜町や茨城県の真壁でも農村改革に取り組みましたが、真壁と言えばうちの母親の実家に近いところ。なんだか親近感を感じます。
二宮金次郎に親近感を覚えた
一方、「小説 二宮金次郎」を読み始めて困ったのは、主人公の二宮金次郎が自分と似ていること。それも、自分のいやなところが金次郎の欠点として描かれていて、閉口しました。
- 一度目標を決めたら執念深く追い続けるところ
- 目標達成のためならば周りの意見を聞かないところ
- ちょっとうまくいくと思い上がるところ
などなど。「あぁ、周りからこういう風に見られるんだな」と反省です。私なんかは、金次郎ほどのカリスマ性がないから、救いようがないですね。
なお、小説として読んだ場合、はやや物足りなさが残ります。まぁ、脚色としては今の売れ線風なので、しょうがないですが。キャラの立った主人公を立てて、周りの人との信頼関係でお涙ちょうだいというのは、ちょっと私のテイストではないかな。もう少し、個人の内面を丁寧に描いてくれると、さらに感情移入できたと思います。
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
- 投稿タグ
- フィードバック
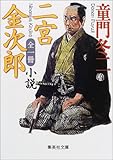
 RSS
RSS