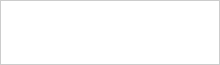最近の日経新聞の面白さたるやタダナラヌものがあるわけですが、その中でも白眉が「経済教室」。
とくに、2月20日(月)の岩本康志東大教授のは面白かった。
西欧社会が発展したのは「大分岐」と呼ばれる19世紀後半の出来事をきっかけとしてである、との説で、経済史が好きな人間にはウヒヒと言いたくなるような論。いわく、
マルサスのわなを終わらせた産業革命を外生的な事件ではなく、
経済発展の過程で内生的に生じる現象として描く
と。
要するに、
マルサスのわな → ミッシングリンク → 近代経済成長理論
ローマーの規模効果
--------------------------
ガローの統一成長理論
という構図みたい。
以下、備忘録的に(文章が今イチ分かりにくかったので、全体像を頭の中で構築できてない)。
アンガス・マディソン「経済統計で見る世界経済200年史」
オデッド・ガロー教授、「統一成長理論」
ポール・ローマー教授、「規模効果」
ロバート・アレン教授「小分岐」
この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。
 RSS
RSS