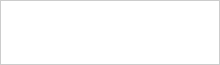「セルフハンディキャッピング」は御社でも起こっているかもしれません。逆に言うと、これを解消できれば職場の生産性が上がるかも。
先週の「MBAの心理学」の中でも面白いなー、と思ったのが、セルフハンディキャッピング
【MBAの心理学】スティーブン・ベルグラスのセルフ・ハンディキャッピングとは、「プライドを守るための言い訳行為」。たとえばテスト前にマンガを読んでしまう。仮にテストの点数が悪かったとしても、「マンガさえ読まなければなー」と、自分以外の原因にして、自分の頭の悪さに直面せずに済む pic.twitter.com/Y6rsZtOmkW
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) October 7, 2024
管理職の方ならば、「こういう部下、いるいる」とお心当たりがあるのでは?
あるいは、ひと頃話題になった「無能の武器化(Weaponized Incompetence)」も近しいものがあるかもしれません。
はたまた、発言前の「前置き」が長いのも似ているかも。会議の際など、「私は知識がないので分からないのですが」、「忙しくてちゃんと見る暇なかったのですが」のように「予防線」を張ってから自分の意見を言うものですね。他の人から、「いや、その考えは違うんじゃない?」と言われても、「すみません、先ほども言いましたが、私は知識がないのです」みたいな言い訳ができるように準備をする行動です。
では、どうやってセルフハンディキャッピングを乗り越える(乗り越えさせる)か。キーワードとしては、行動アプローチ、心理的安全性、自己肯定感あたりが関係すると思うのですが…
自己肯定感が他者の否定に繋がるとき
この自己肯定感がなかなかくせ者というのがこちら。
【MBAの心理学】自尊心(自身の中の問題)とナルシシズム(自身と他者の比較)は別概念。しかし、暴力行動研究の大家、オハイオ州立大学のブッシュマン等によると、1970年代から欧米では自尊心を高める子育てが中心になり、それがナルシシズムの高まりを生み出してしまった可能性がある pic.twitter.com/DBxJ5qrmze
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) October 9, 2024
職場でも、部下の自己肯定感を高めるはたらきかけが思わぬ方向に行ってしまう可能性が示唆されます。
結局のところ、「魔法の杖」のような解決策はなくて、その時の状況、その部下のキャラクターに応じて使い分けていくしかないのでしょう。そのためにも、管理職の方にはいい意味での「トライアンドエラーによる血肉化」を勧めたいですね。

この記事を書いた人

木田知廣
MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。
ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。






 RSS
RSS