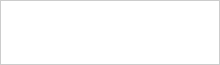メルマガ MBAの三冠王 Vol.422娘の一言から始まった、意外な未来戦略
終活していますか?
私もそんな年ではないので気にしていませんでした。
ところが先日、娘が真顔で言うわけです。
パパに何かあったとき、手続きとかわからないよね?
と。
たしかに……
ということで、さっそく本屋で終活ノートをチェック。
そこにあった意外な発見は……
メルマガ MBAの三冠王 Vol. 420 仕事で成果を出す人は、なぜ「温活」するのか
まずは業務連絡から。
2月18日(水)、「問題解決」の勉強会を行います。
https://corporate.ofsji.org/kouza/logictree/
無料です。が、一つだけご注意を。
よくあるウェビナー形式の録画配信ではありません。
顔出しあり、双方向ありの、真剣勝負。
思考の筋肉を動かしたい方は、お早めにお申し込みください。
では本題。今日のテーマは「温活(おんかつ)」。
これ、単なる「冬の冷え性対策」だと思ったら、大間違い。
実は今、温活は「マインドフルネス」の最短ルートとして注目されています。
具体的な実践例は……
メルマガ MBAの三冠王 Vol.419 AIに仕事を奪われないための、「私の」取り組み
最近のAIの進化を見ると、思いませんか?
「自分の仕事、いらなくなるのでは?」
私はあります。というか、確信しました。
「3年以内に、間違いなくAIに仕事を奪われるな」と。
なので、考えました。
この流れに同対抗しよう、と。
結論は…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.419 仕事で成長できる人が年末にやる「あれ」の話
仕事で成長したい人が年末年始にやる「あること」をご存知でしょうか?
それが、自分の資産状況の棚卸し。
「え?お金の話?」
「それ、ビジネスでの成長と関係ある?」
と思うかもしれませんが、大アリ。
金銭面の不安が強い状態では、無意識のうちに“守りの選択”をしてしまいます。
失敗しそうな挑戦を避け、無難な仕事をこなすだけ。ましてや転職なんてとんでもない!
結果として、成長の機会そのものを遠ざけてしまうのです。
逆に、生活や将来に対する安心感があると、「失敗しても立て直せる」という心理的余裕が生まれます。
この余裕が新しいチャレンジへの原動力となり、チャンスと成長につながるのです。
少しマニアックな整理ですが、ビジネスパーソンの成長には、
- 金融資本 (金銭面)
- 人的資本 (スキル・体調面)
- 社会資本 (人脈・信用面)
という3つの資本がもれなく必要なのです。
このメルマガ読者の方ならば、人的資本の重要性はおわかりでしょう。
でも、それ「だけ」ではダメ。
金融資本が不安定だと、成長は長続きしません。
…とここまで聞いて、
自分は大丈夫。NISAでオルカン買ってるし
と思った方、要注意かも。
なぜかと言うと…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.418 リーダー必見の問題解決講座リリースしました
仕事で、「どう取り組めばよいかわからない……」と悩むときってありますよね?
その悩みを解決するのが分解。
大きな課題は小さく分割して解決
が王道です。
この方法論が学べる動画講座を公開しました。
●リーダーのためのロジックツリー講座
https://www.udemy.com/course/mba-logictree/
問題を分割する方法論、「ロジックツリー」と呼ばれます。
ひょっとしたら、研修やセミナーで学んだことがあるかもしれません。
ただ、意外なほど多くの人が、その本質を知りません。
どういうことかというと…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.417 ライバル企業を丸裸にする有価証券報告書
市場調査に続いて、ライバル企業の調査法です。
題材は、「ジャストシステム」。
私は製品の日本語入力ソフトATOK (エートック)の昔からのファンでした。
ところが、最近大幅値上げの値上げ。
月額330円が倍の660円に!
これはちょっと……、と、泣く泣く解約。
でも、気になるじゃないですか。
なぜこんなにも唐突に値上げをしたのか?
見えてきたのは、「ミルキング戦略」です。
メルマガ MBAの三冠王 「データ駆動採用」への道しるべ
採用力のある企業の特徴って御存知ですか?
世の中は人手不足で、今や人材獲得競争真っ只中。
その中で頭一つ抜けだすために必要なのは……
お金?給料が高いことでしょ?
はもちろん正解。
ただ、それ以上に大事なのは「データ」。
あのGoogleも実践している、データ駆動型<ドリブン>人事がその答えです。
その確かな道標となるのが…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.415 「働いて働いて……」の裏にあるプレゼン力UPの秘訣
まずは業務連絡から。
youtubeショートの投稿を再開しました。
https://www.youtube.com/@kidatomohiro
ビジネスに効く“1分インプット”を発信中。
フォローしていただけると、更新の励みになります。
では、本題。
今年の流行語大賞が、高市早苗首相の「「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」に決まりました。
あのフレーズを聞いた瞬間、正直私は「うまいな」と思いました。
もちろん、前任者がアレだったせいで相対的に際立っている、という説もありますが……
とはいえ、高市首相の“伝える力”が抜きん出ているのは事実。
では、なぜ彼女の言葉は国民にスッと入ってくるのか?
その秘密を解き明かすのが「ダイヤモンドモデル」です。

どういうことかというと……
メルマガ MBAの三冠王 Vol.414 お宅のサイバーセキュリティ、大丈夫?への対策
まずは業務連絡から。
以前紹介した会計のKindle書籍の紙版が出版
されました。
●会社の健康状態をすぐに見抜ける決算書超入門
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34M1N4D
薄い本ですが、内容はしっかりしていますので、紙で読みたい方はぜひ手にとって下さい。
なお、スマホで読みたい方はこちらから。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4KM24PV
御社のサイバーセキュリティ、大丈夫でしょうか?
と聞かれたらドキッとしますよね。
最近、一流企業でもサイバー攻撃の被害に遭っています。
対策しなきゃいけないのは分かるけど、どうしたら…!?
というときに、チェックしたい本を紹介します。
私も最近読んだんですが、ビックリ!
ハッキングって、こんなに簡単なんだ…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.413 戦略の達人が密かに使う「リアルオプション」
先日、ベネッセさんのイベントに登壇した際のアーカイブ動画をいただきました。
戦略をサクッと学びたい人は、ご覧いただけると幸いです。
1ヶ月ほどの限定公開らしいです。ご興味がある方はお早めにどうぞ。
●MBA流フレームワークで学ぶ 実践的戦略立案
詳しく学びたい方は、もちろんUdemy講座で。
来週月曜日まで有効の最安クーポンも発行しましたので、使ってください。
●リーダーのための戦略講座
https://www.udemy.com/course/mba-senryaku/?couponCode=2CCABD
クーポンコード:2CCABD
有効期限:11月24日(月) 23:59
では、ここから本題。
戦略の上級編です。
若干難易度が高いのですが、ビジネスを
成功させる達人のワザを紹介します。
株主優待をもらったので吉野家に行ってみた
株主優待券をいただいたので、吉野家さんに行ってきました。そこでみた、戦略の進化は…
吉野家と言えばカウンターで注文のはずが…
吉野家さんと言えば、私の戦略講座で取り上げさせていただいていて、勝手に恩義を感じています。集合研修を承ったことはないのですが、海外に行く前の社員の方を個別指導させていただいたことはあって、えらく優秀な方だな~、と感銘を受けたのも思い出します。
そんなご縁もあり、私は吉野家さんの株主です。先日株主優待券をいただいたので、お店に行ってきました。そこで驚いたのが…
オーダーがタブレットになっている!
吉野家の「勝ちパターン」はリピーター獲得
吉野家さんと言えば、カウンターで注文が当たり前。ただ、女性客をターゲットにした「黒吉野家」(クッキング&コンフォート店)では、流石に「大盛り一丁!」と大声を出すわけにはいかないので、タブレットでの注文だったのですが…ついには通常の店舗でも導入とは。
私がなぜこれほどタブレット端末にこだわるかというと、吉野家さんの強みの根幹を脅かす可能性があるから。私の戦略講座を受講いただいた方はご存じのとおり、あえて券売機もタブレットも使わずに口頭で注文を受けつけることにより、お客様からカスタマイズを誘発し、リピーター化する効果が見込まれます。
さらに極論すれば、注文すら不要。なじみのお客様の顔を見ただけで、「この人はつゆだくだ」とスタッフが理解して提供する…それが強みのはず。
しかし、タブレットで注文となると、カスタマイズできません。ましてや、なじみのお客様の顔を覚えるというのもないでしょう。ほんとうに大丈夫かな、と株主としては心配になります。
ちなみに、最近の株価を見てみましょう。日経平均が爆騰している中、吉野家さんの株価は3,000円あたりをウロウロしていてパッとしません。私の心配もあながち杞憂とは言えないでしょう…
と、思いきや、大丈夫です。
ヒトモノカネをラーメン事業に集中する吉野家
実は吉野家さんは今、新たな戦略としてラーメン店による世界進出を追求しています。海外の方に日本のラーメンが人気なのはご存じのとおりですし、長年の懸案であった客単価向上も実現できます。社内のリソース、ヒトモノカネをラーメン事業につぎ込むためにも、既存の牛丼事業は軽量化を図っているのが、タブレット端末による注文方式というのが私の見立てです。
つまり、今は冴えない株価も、ラーメン事業が成功した暁にはドカンと跳ね上がる、はず。と、期待したいですね。
 Photo by benson-ho
Photo by benson-ho
メルマガ MBAの三冠王 Vol.412持ち家vs賃貸 - MBA講師がマンガで学ぶリアルな資産戦略
自宅は賃貸派ですか?持ち家派ですか?
私は賃貸派。
理由はシンプルで、「何千万円もの借金を背負うのが怖い」。
しかし、最近その信念が少し揺らいでいます。
そこで、不動産業界の調査から始めました。
具体的には「あの」マンガです……
見直されつつあるパワハラする人の性格特性
パワハラする人の共通項で注目された「ダークトライアド」という性格特性。でもいま、見直しの機運が高まっているようです。
ダークトラアド=キャベリアニズム x サイコパシー x ナルシシズム
まずはダークトライアドの定義から。これは、
- マキャベリアニズム
- サイコパシー
- ナルシシズム
という特性を持った性格、となります。
なんとなくイメージは分かりますよね。職場にいる邪悪な「アイツ」のことだとピンとくる方も多いはず。
そしてこのダークトライアドが注目を集めたのは、パワハラをする人は、まさにこれと指摘されたことがキッカケです。
フレームワークとしては稚拙なダークトライアド
でも、個人的にはこのダークトライアド、ピンときませんでした。だって、「マキャベリアニズム」って測定できるの?って疑問に思いますよね。
しかも、この3つの要素って実は相関関係が高くて、ナルシシズムでサイコパシーだからマキャベリアニズムになっていると考えられます。
なので私は、こんなツイートをしたことがあります。
【MBAの心理学】(要検証)デルロイらが提唱するパワハラ行為者に特有の性格的傾向が「ダークトライアド」、マキャベリアニズム、サイコパシー、ナルシシズムからなる。もっとも、その3つは相関しているので、フレームワークとしては稚拙か #心理学 #MBA pic.twitter.com/5dxQSeFpoS
— 木田知廣 (マサチューセッツ大学MBA講師) (@kidatomohiro) December 22, 2024
そしたらやっぱり、学問の世界でも見直されてるそうじゃないですか。
ダークトライアドではなくアンタゴニズム
詳しくは鈴木祐三のブログに譲りますが、
あいまいすぎて、結局よくわからない
とのこと。そりゃそうだ。
そして、ダークトライアドに変わっては「アンタゴニズム」という性格特性が提唱されている、と。
津野香奈美先生のパワハラ上司を科学する (ちくま新書 1705)を踏まえると、
アンタゴニズム x 外向性
がパワハラする人の共通点とまとめた方がすっきりしますね。

日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト30」に思う
日経トレンディさんから「2026年ヒット予測ベスト30」が発表されました。例によって、「知っているか知らないか」でチェックすると…
日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト30」は9勝21敗
来年ヒットしそうな商品30選を日経トレンディさんが選んだのが「2026年ヒット予測ベスト30」。チェックしてみたら……知っていたのはわずか9個。それも、「どこかで聞いたことがある」を含めてなので、自分の感度の低さに危機感を覚えそう。
でも、実はこれって別に恥ずかしい話じゃないんです。なんせ「未来予測」なんて、当たるも八卦。予測の段階で全員が知っていたら、そりゃもう“予測”じゃなくて“既定路線”です。
日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト30」の傾向
毎年のことですが、日経トレンディさんはなかなか攻めた商品を挙げています。多言語リアルタイム翻訳、中古EV、生成AIショッピング……未来感と生活感が絶妙に混ざり合っていて、これは分かる。一方で、「スプレー型香水自販機」や「夜ヨーグルト」「コンビニRVパーク」など、話題先行の気がしますね。スプレー型香水、誰がどう使うんだろう?
全体を眺めると、世のトレンドは2つのベクトルに分かれていて、ひとつは、“苦労キャンセル系”――手間や不便、ちょっとした気まずさをそっと消してくれるサービス。そしてもうひとつは、“エコノミー・グルメ系”――物価高の中でも「ささやかな贅沢」を取り戻したいという欲求。
私が個人的にひとつだけ強く推すとしたら、
常温保存できる「生パスタ」。
冷蔵も冷凍も不要。保存性が高いのに食感は“生”。
これ、生活者の感情とロジスティクスの両面を一気に射抜く、かなり強いカードじゃないですか?
トレンドは“知っているかどうか”ではなくて、“なぜ選ばれそうなのか”。
このランキングは、未来の生活者インサイトを読むためのヒントの宝庫かもしれません。来年、いくつ的中するのか……ちょっと楽しみになってきました。
日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト30」
| 商品 | 知っているか |
|---|---|
| 1位 多言語リアルタイム翻訳 | ○ |
| 2位 中古EV | ○ |
| 3位 スプレー型「香水」自販機 | ○ |
| 4位 生成AIショッピング | ○ |
| 5位 ザ・ブレスコ | × |
| 6位 「常温保存」生パスタ | ○ |
| 7位 SuiSui(スイスイ) | × |
| 8位 のびっこピクニック | × |
| 9位 ステーブルコイン(円連動) | ○ |
| 10位 Pokemon LEGENDS Z-A | × |
| 11位 夜ヨーグルト | × |
| 12位 トイデジ | ○ |
| 13位 超・保存技術「ZEROCO(ゼロコ)」 | × |
| 14位 「セルフ式」コンビニラーメン | × |
| 15位 Rakuten最強衛星サービス | × |
| 16位 キレキラ!ワイパー ドライ×ウエット シート | × |
| 17位 生のときしっとりミルク | × |
| 18位 奈良監獄ミュージアム | ○ |
| 19位 推し化カラオケ(推しカラ) | × |
| 20位 IDARE(イデア) | × |
| 21位 KEY DOORS+ JET BREW | × |
| 22位 ソフィおでかけ交換ショーツ | × |
| 23位 竜宮国 | × |
| 24位 冷食・アイス「食べ放題」の日 | × |
| 25位 MOCOLA(モコラ) | × |
| 26位 トライアルGO | × |
| 27位 金麦ビール | ○ |
| 28位 高還元デビットカード | × |
| 29位 ムーニー みらいのお肌のために 低刺激であんしん | × |
| 30位 コンビニRVパーク | × |

メルマガ MBAの三冠王 Vol.411 ベネッセさんのイベントに登壇します
先週ご案内したとおり、ベネッセさんのイベントへの登壇が決まりました。
・日時:2025/11/19(水)12:10 – 12:50
・講座名:MBA流フレームワークで学ぶ
実践的戦略立案 【学習トレンドLIVE講座】
・費用:無料
・参加:https://qrtn.jp/a4799
この↑URLは、ウェビナーに直接入室できますので、時間が来たらクリックください。
問題意識は、
日本企業には戦略がない
ことにあります。
いや、私が言ってるんじゃなくて、指摘したのは「あの人」… (さらに…)
流行語大賞ノミネート30語、どのくらい知ってる?
今年の流行語大賞のノミネート30語が発表されました。昨年も感じましたが、知らない単語が増えているのは価値観の多様化の表れでしょう。
下記、ノミネートされた言葉を知っているか否かで○×をつけてみました。結果は、21勝9敗。けっこう知っている感じですかね。
ただ、「薬膳」とか、言葉は知っていますが流行になっているとは知らなかったので微妙ではありますが。
ちなみに予想をすると、流行語大賞を受賞するのはズバリ、「ミャクミャク」。政治の世界でもイシンが躍進したので、その象徴として取り上げられそうな予感。
| ノミネートされた言葉 | 知っていたか |
|---|---|
| エッホエッホ | × |
| オールドメディア | ○ |
| おてつたび | ○ |
| オンカジ | ○ |
| 企業風土 | ○ |
| 教皇選挙 | ○ |
| 緊急銃猟/クマ被害 | ○ |
| 国宝(観た) | ○ |
| 古古古米 | ○ |
| 7月5日 | ○ |
| 戦後80年/昭和100年 | ○ |
| 卒業証書19・2秒 | ○ |
| チャッピー | ○ |
| チョコミントよりもあ・な・た | × |
| トランプ関税 | ○ |
| 長袖をください | × |
| 二季 | ○ |
| ぬい活 | × |
| 働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相 | ○ |
| ビジュイイじゃん | × |
| ひょうろく | × |
| 物価高 | ○ |
| フリーランス保護法 | ○ |
| 平成女児 | × |
| ほいたらね | × |
| 麻辣湯(マーラータン) | × |
| ミャクミャク | ○ |
| 薬膳 | ○ |
| ラブブ | ○ |
| リカバリーウェア | ○ |

メルマガ MBAの三冠王 Vol.410 高市総理の「伝える力」は前任者とどう違う?
まずは業務連絡です。
ベネッセさんが主催する「学習トレンドLIVE講座」に登壇することになりました。
日にちは、11月19日(水) 12:10〜12:50。
Zoomウェビナー開催なので、お時間が合う方はぜひ。
内容は、もう少し固めてからまたご連絡します。
では、本題。
リーダーとして信頼される人って、何が違うんでしょうか?
人格や能力はもちろんですが、忘れてならないのは、
伝える力
そんなことを感じさせてくれるのが、高市早苗総理大臣です。
スピーチが上手なのはご存じのとおりですが、実はそこには私たちも学べるコツがあります。
それが、PEMAの法則。
どういうものかと言うと…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.409 プロンプト付き: ChatGPTのリサーチ機能
ChatGPTの「ディープリサーチ」機能、ご存じでしょうか。
普通のモードで使っているときは、聞いたことにパッと答えてくれる。
ただ、そこには誤情報<ハルシネーション>も混じっているのが要注意……
というのは、「これまで」の話。
ところがDeep Research機能では……
最後にプロンプトも掲載しているので、ぜひ使ってください。
メルマガ MBAの三冠王 Vol.408 外圧でしか変われない国のゆく末
日本の政治が大きく変わる気配をプンプン感じています。
高市総裁に期待?
いえいえ。
総裁選で「解党的出直し」と言っていた割には、閣僚はどこかで見たメンツ…
もちろん頑張ってほしいのですが、それほど期待は持てません。
むしろカギになるのは外圧。
過去400年間振り返ると、この国が本当に変わるには外圧が必要と分かります。
どういうことかというと…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.407 なぜか出世する「あの人」の裏の顔
出世できる管理職と優秀な管理職の違いってご存じですか?
え?出世できる=優秀じゃないの?
と思うかもしれませんが、現実はこの両者は異なります。
実際身近に、「なぜあの人が昇進したんだ?」と思うような管理職もいるのでは?
そしてこの両者の違いはズバリ、時間の使い方。
仮に管理職の仕事を以下の4つのカテゴリーに分けたとします。
- 管理業務
- コミュニケーション
- 部下マネジメント
- 人脈づくり
出世できる管理職は、どこにもっとも時間を使っているでしょうか?
(詳しい定義はメールの末尾に)
ちなみに時間の使い方のグラフはこちらをご覧ください。

メルマガMBAの三冠王 Vol.406 佐賀でサッカーを見て気づいた戦略の話

サッカーサガン鳥栖の試合を、ホームスタジアムで見てきました。
【佐賀県とは縁もゆかりもない私がサガン鳥栖にハマったわけはこちら】
https://kida.ofsji.org/archives/4881
いや~、新鮮。
いつも関東近辺のスタジアムに行くと、完全アウェー。
スタジアムの隅っこで小さくなって応援しています。
それが、周りはみんな鳥栖サポというのは、なんともうれしい体験でした。
試合も、4-2で快勝!
わざわざ出張の合間に時間をとった甲斐がありました。
ただ…
クラブ運営というビジネス面で考えると、この先もちょっと厳しそう。
そこで私の提言は…。キーワードは、「強者の戦略、弱者の戦略」です。
書評「小説 二宮金次郎」~偉大なる農政家の足跡
「二宮金次郎」ってどんなイメージがありますか?銅像の、薪を背負って本を読んでいる人…というのが多くの人の一致するところでしょう。
でも実際は、それはごく一部。本当は奥の深い農業/農政の改革者だと気づかされました。それが、童門冬二先生のご著書、「小説 二宮金次郎」です。
二宮金次郎が説く、褒めると叱るの比率
私が二宮金次郎に興味を持ったキッカケは、「フィードバック」から。現代の欧米においては、「ゴットマン比率」と呼ばれる、褒めると叱るの適正割合が研究によって提唱されています。では、日本はどうなんだ?というときに出てきたのが、二宮金次郎の言葉。
可愛くば、五つ教えて三つ褒め、二つ叱って良き人となせ
ゴットマン比率よりも「叱る」の割合が高くなっていますが、それは日本では、ましてや昔の農村社会では人間関係が固定的だったためと考えれば納得です。
そして、この延長線上で「いもこじ」という言葉に行き当たりました。これは、グループ討議によってアイデアの洗練、人間の徳の向上ができるというもので、まるで水を張った桶に里芋を入れてぶつけ合うと汚れが落ちる様子から名付けられたものです。このような農村変革手法を確立しているということで、ガゼン興味を持ったのです。
組織変革者、二宮金次郎
実際に「小説 二宮金次郎」を読んでみると、
想像よりも深かった
というのが率直な感想。二宮金次郎の改革は、実は農村だけでなく、その農村の所有者たる武士階級までおよんだというのがビックリです。考えてみれば当時は6公4民などの超重税社会。武家の台所が苦しいままでは農村が裕になるはずもなく、言われてみれば当然と気づきました。
ちなみに、二宮金次郎は小田原生まれで、当時の小田原藩主は大久保家。有名な「彦左衛門」の家系(直系ではない)。そういえば、徳川草創の頃からの忠臣であった大久保家は、江戸幕府設立後は冷遇されていた、なんて話を聞いたことがあるような気がします。つまりは小田原藩も火の車であったがゆえに、農民階層宇出身の二宮金次郎が活躍する余地があったと言えましょう。
その後は栃木県の桜町や茨城県の真壁でも農村改革に取り組みましたが、真壁と言えばうちの母親の実家に近いところ。なんだか親近感を感じます。
二宮金次郎に親近感を覚えた
一方、「小説 二宮金次郎」を読み始めて困ったのは、主人公の二宮金次郎が自分と似ていること。それも、自分のいやなところが金次郎の欠点として描かれていて、閉口しました。
- 一度目標を決めたら執念深く追い続けるところ
- 目標達成のためならば周りの意見を聞かないところ
- ちょっとうまくいくと思い上がるところ
などなど。「あぁ、周りからこういう風に見られるんだな」と反省です。私なんかは、金次郎ほどのカリスマ性がないから、救いようがないですね。
なお、小説として読んだ場合、はやや物足りなさが残ります。まぁ、脚色としては今の売れ線風なので、しょうがないですが。キャラの立った主人公を立てて、周りの人との信頼関係でお涙ちょうだいというのは、ちょっと私のテイストではないかな。もう少し、個人の内面を丁寧に描いてくれると、さらに感情移入できたと思います。
MBAの三冠王 Vol.404 いまのJALに必要なのは、厳しさではなく●●
JAL (日本航空)が揺れています。
キッカケは、パイロットの飲酒問題。
アルコールが抜けない機長のせいで、フライトが遅れることたびたび。
国土交通省から3回も警告を受けています。
これに対してJALの鳥取社長が言うのは、
対応が甘かった。乗務員の監視をしてきたが、本当の意味で管理ができていたかというと、最終的には(中略)見逃していたところがあった
と。
いやいやいや。
これ、見当外れの対策ですよ。
むしろ今のJALに必要なのは……
メルマガ MBAの三冠王 Vol.403 7割の管理職が誤解している1on1で話すこと
1 on 1と言う言葉、すっかり根付いた感があります。
ところが、そのやり方となると、意外なほど多くの人が誤解をしているもの。
私は研修講師として多くの管理職の方と話しますが、効果的なやり方を理解しているのは3割ぐらいと言うのが肌感覚です。
特に、「何を話すか」に関しては誤解が多いもの。
1 on 1は業務の話をする時間ではありません
と言って、
部下のキャリアの話をする時間でもありません
では、何を話すか?
その意外な正解が…
ちなみに、よく詳しく知りたい方向けの無料勉強会の参加受付中です。
メルマガ MBAの三冠王 Vol.402 「頑張っても報われない」…そんなときは足元を見直すべき

語学って、スマホのおかげで身近になりましたよね?
私がいま取り組んでいるのが中国語。
善し悪しは別にして、この先中国のプレゼンスが高まることは間違いありません。
だとしたら、勉強しておいて損はなし。
ところが。
中国語の発音、いつまでたってもうまくならないのです。
アプリに課金して、けっこう頑張ってるつもりなんですけどね。
練習するたびにダメ出し。何度やっても「不合格」。
だんだんと私も疑心暗鬼になって、
このアプリ、おかしいんじゃない?
と思ったその矢先、あっさり解決しました。
その秘訣が…
-・-・-・-・-・-・-・-・-
あらためまして、こんにちは。
「MBAの三冠王」こと、
シンメトリー・ジャパン代表の
木田知廣です。
※MBAとは…末尾でご紹介しています
-・-・-・-・-・-・-・-・-
中国語には、ピンインと呼ばれる発音記号がついてきます。
私の苦手と言えば、「彼」を指す中国語の「他」。
発音は単純で、そのまま「Ta」です。楽勝…
のはずが、毎回アプリにダメ出しされます。
他にも、
K、Q
から始まる音がぜんぜんダメ。
と、ここまで来て、中国語が堪能な人は気づいたはず。
実は私が苦手な音には共通点がありました。
それが、「有気音」。
中国語には息の吐き出し方による区別があって、息を強く出す有気音が苦手だったのです。
有気音のポイントは、最初の子音と母音の間に息を乗せること。
先ほどの「他」で言えば、
T (息) a
とわずかに間をおくイメージです。
試してみると、アプリがOKを出してくれて、ビックリです。
何事もコツってのはあるものだなぁ…と感心していましたが、いや、感心している場合じゃなかった。
実はそのコツ、私が昔買ったNHKのテキストにバッチリ載っていました。
2018年4月号を見直して、気づいた次第です。
7年間も、何やってたんだか…
語学に限らず、新しいことを身に付ける際、基礎をおろそかにしてはいけないんですね。
身にしみて感じました。
メルマガ MBAの三冠王 Vol.401 「管理職?イヤです」から「意外と悪くない」へ~53.3%の希望とは?
まずは業務連絡です。
9月10日(水)に「部下に的確にフィードバックできるようになる」ための勉強会を開催します。
https://corporate.ofsji.org/kouza/leadership/1on1/
詳しい内容はまた後日お知らせしますが、メルマガ読者の方には一足先にお知らせです。
問題意識のある方はぜひご参加ください。
あ、参加費は無料です。
さて、本題。
「管理職になりたいですか?」
最近の若手に聞くと、答えはノー。理由は、
「だって、たいへんそうじゃないですか」
と。
まぁ、そう見えるよなぁ…
でもね。
アンケートからは意外な真実が見えてきます。
管理職になりたくない人が、実際に管理職になったら、何と言うでしょうか…?
メルマガ MBAの三冠王 Vol.400 漢方「だけ」じゃなかった、私の化学物質過敏症克服記
メルマガ MBAの三冠王 Vol.399 知らなかったら損をする「選択的週休3日制」の真実
「週休3日」って、どう思います?
実はイギリスでは、大規模な先行テストが行われました。
90社で半年間テスト的に実施したところ…
- 仕事の成果は維持できた
- 従業員満足度は95%
そんな結果が出ました。
まぁ、「給料は下げない」という前提でのテストなので、当然かもしれませんが…
日本でも今、「選択的週休3日制」が動き出しています。
この動き、アリかナシかというと…
メルマガ MBAの三冠王 Vol.398 パワハラじゃない叱り方はAIに訊け!
人に厳しいことを言うのって、できれば避けたいですよね?
特に上司と部下の関係だと「これってパワハラにならないかな…」と心配になってしまう。
本当は言った方がいい。
むしろ成長のためには必要。
でも、言わない。
そんな経験、ありませんか?
でも、時には「耳の痛いこと」も、ちゃんと伝える必要があるんです。
なぜならば、最近の若手社員は、自分が成長できない「ゆるい職場」を嫌うから。
詳しくはこちら↓
https://kida.ofsji.org/archives/5125
では、どうすれば上手にフィードバックできるのか。
答えが、「人工知能を相手に練習する」こと。
実際に私も試してみたのですが…
まさか、ここまでとはな
メルマガ MBAの三冠王 Vol.397 朗報:「自分の性格を直したい」には方法論があった
自分の性格で「ここだけは直したい」ってありますか?
私だったら、執念深いところ。
よく言えば、粘り強い。
でも悪く作用すると、過去のイヤな思い出をいつまでも覚えていて、「いつかはやり返してやろう」と復讐の囚人になってしまいます。
でも、そういうのって持って生まれたものだし…
と思っていましたが、実はスキルによって克服可能なんですって!
ホントか?と思ったその研究結果というのが…
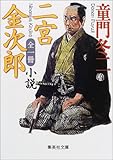

 RSS
RSS